SANNOリーダーシップ開発フォーラム関西2018

2018年12月18日(火)に、NHK連続テレビ小説「まんぷく」プロデューサーの堀之内礼二郎氏をお招きし、「次世代を臨むリーダー育成を考える~触発のデザイン 共に育つリーダーたち~」を開催しました。
【開催概要】
会場:梅田スカイビル タワーウエスト36F(大阪府大阪市北区大淀中1-1)

ゲストカタリスト:NHK大阪放送局 制作部(ドラマ)
プロデューサー 堀之内 礼二郎 氏
プロフィール
2012年にはロサンゼルスに渡り、ハリウッドのプロデュース術を学ぶ。
現在は大阪放送局にて、主に朝ドラ制作に従事。2018年下半期の連続テレビ小説「まんぷく」のプロデューサーを務める。
これまで携わった作品は大河ドラマ「天地人」「花燃ゆ」、朝ドラ「ゲゲゲの女房」「梅ちゃん先生」「べっぴんさん」、スペシャルドラマ「坂の上の雲」など。

本学カタリスト
学校法人産業能率大学 総合研究所 経営管理研究所
主任研究員 岩元宏輔
※所属・肩書は掲載当時のものです

はじめに ~セミナー主旨~
この問いは、多くの企業が抱える人材育成課題のひとつではないでしょうか?
今、世の中で活躍している若きリーダーのふるまいや考え方に注目してみると、必ずしも先頭に立って陣頭指揮を執るようなリーダーではないようです。多様なスタイルでリーダーシップを発揮している若者の姿を皆さんもよく目にすることでしょう。
このセミナーは、「教わる」セミナーではなく、「新たな気づきをきっかけに、自分ごととして考える」セミナーです。
今回のゲストカタリストは、現在放送中の朝ドラ「まんぷく」のプロデューサー堀之内礼二郎氏です。カタリストとは、新たな気づきを得るための、触発のきっかけを提供する存在。異なる世界で活躍しているカタリストを媒介に、さまざまな視点からの刺激を受けることで、リーダー育成について、本気で語り合う場を提供させていただきました。
プログラム構成 15分×6話
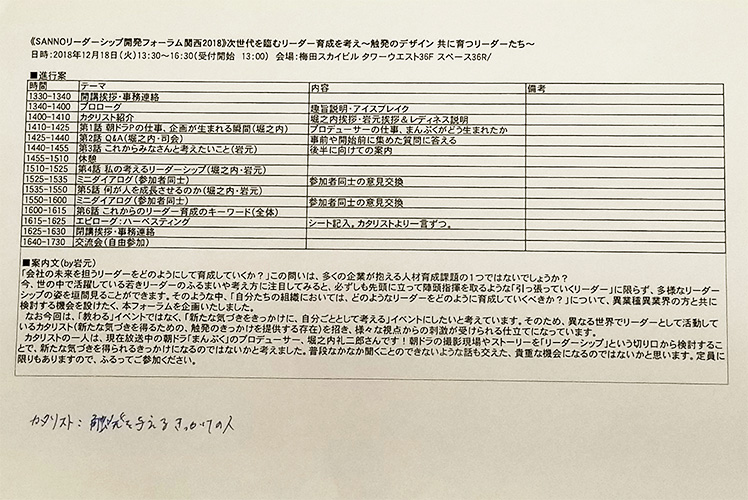
第1話 企画が生まれる瞬間(堀之内氏)
ただし、朝ドラには、各回15分で計150回分のストーリーが展開できるものであること、女性が主人公であること、朝見て気持ちのいいものであることなどの制約条件があります。
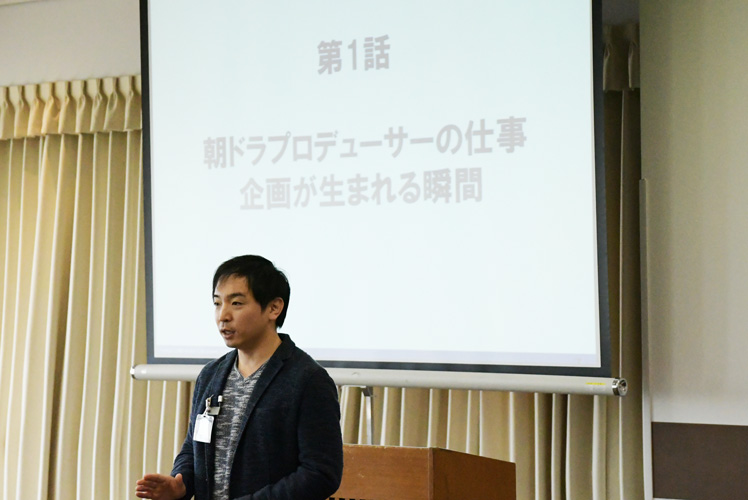
そこで、誰もが知っていて利用している、「コンビニ」をテーマにドラマが展開できないだろうかと考えました。実際にコンビニに足を運んでみると、「インスタントラーメンの棚の獲得が最も競争が激しい。」という、食品メーカーの営業を経験したことがある妻の言葉が頭をよぎったのです。確かにインスタントラーメンはコンビニの中でも多くの棚を占領しており、とりわけ日清食品さんの商品が圧倒的なシェアを占めていました。「インスタントラーメンでドラマが作れないだろうか。」直感的なひらめきがあった瞬間と言えます。
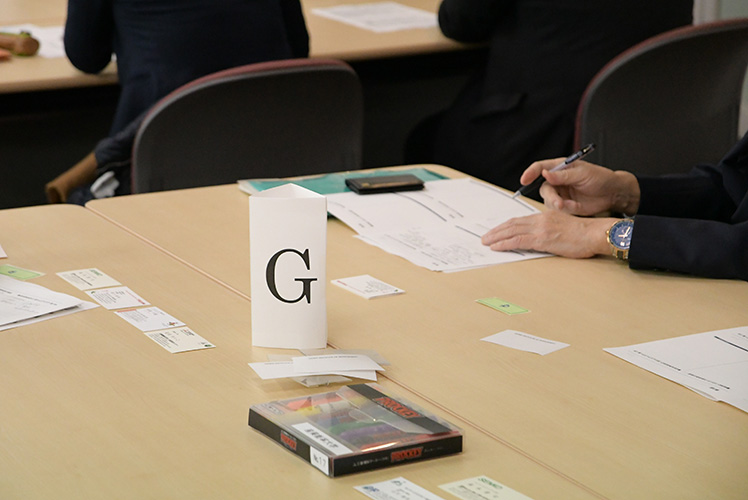
第2話 参加者からの質問に堀之内氏が答えます
Q:萬平(百福)さんのような職人気質のリーダーを育てるためには、どのようなポイントがあるでしょうか。
A:今回のドラマは萬平さんの妻である福子さんが主人公です。しかし、そのまま描いたのでは、いろいろなものを開発する萬平さんがどうしても目立ってしまうため、福子さんの母である鈴さん(頑固キャラ、お決まりのセリフは「私は武士の娘です」)を登場させています。萬平さんと鈴さんの間に立って、場をうまく取り仕切る調整役の福子さんを描くことで、福子さんがいつも話題の中心にいてくれます。正に福子さんは組織でいうところの中間管理職。こちらも立てつつ、あちらも立てる。組織でも福子さんのような中間管理職の存在が職人気質のリーダーを育てることに繋がるのではないでしょうか。
Q:プロデューサーとして一番苦労したことは何でしょうか。
A:企画や構想をちゃんと伝え、各所に通していくことが大変でした。協力して欲しい、という思いを伝えつつも、なかなか思い通りにことは運びません。正直、何度も壁にぶち当たりました。ただ、それでも本当に大事だと思うことに関しては、決してあきらめませんでした。粘り強く情熱を伝え続けること、そしてその熱を自分の中に持ち続けることを大事にしてきました。
Q:朝ドラに選ばれるために、会社としてどのような広報活動をすればよいでしょうか。
A:実際のところ、大河ドラマや朝ドラは、「地元の英雄を主人公にしてほしい」「うちの会社の創業者をドラマにしてほしい」というオファーもたくさんきます。しかし、売り込まれたところで企画の遡上にのることはめったにありません。「選ばれるために」頑張るのではなく、地道にステークホルダーに向けた広報活動をおこなっていくこと。そしてその際、会社側が言いたいことだけではなく、ちゃんと外部の無関係な人にもちゃんと伝わる視点を心がけることが、結果的に近道になるのではないでしょうか。
第3話 これから皆さんと考えたいこと(岩元研究員からの問題提起)
組織行動論の分野で最も研究されているテーマの1つでありながら、まだまだ解明されていないことが多いのが、本日のテーマである「リーダーシップ」です。学者の数ほどリーダーシップ論が存在するとも言われています。だからこそ、リーダーシップについては自分なりの考えが必要です。
まずは、皆さんの組織内では、どのような人材育成、リーダー育成の取り組みをされているのか、グループ内で共有してみてください。
※グループ内でミニダイアログ
お題:現状、どのような人材育成、リーダー育成の取り組みをされていますか。
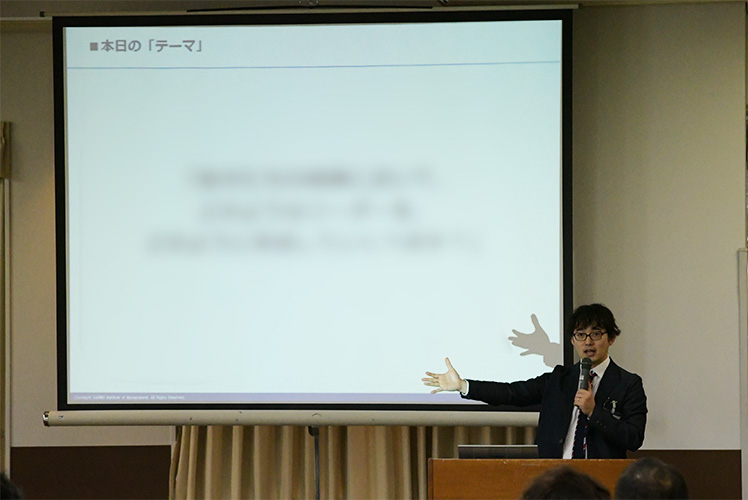

第4話 私の考えるリーダーシップ(堀之内氏&岩元研究員)
— 岩元
早速ですが、堀之内さんにとって、リーダーシップを一言で言うと何でしょうか?
— 堀之内氏
私にとってのリーダーシップは、自分はリーダーであるという「意識」だと思います。立場や職責上のリーダーではなくても、どんな人も、自分の人生のリーダー(主人公)は自分です。自分で考え、行動する。「リード・ザ・セルフ」という言葉がありますが、“自分自身を自ら引っ張る”という自覚を持つことがリーダーシップに必要だと思います。
NHKには、自らの専門性に基づき、自ら考える文化があるように思います。朝ドラのチームは制作、技術、美術、広報、編成など、様々な専門性を持ったスタッフで作られます。少なく見積もっても150人ほどの体制になるでしょうか。台本を渡すとプロデューサーが指示を出さなくても皆がそれぞれの考えの基に動きます。自らの持ち場に責任を持ちつつ、「リード・ザ・セルフ」をすることができる。だからチームとしても強いのでしょう。
そこで私は皆さんに問いたい。
「あなた自身は燃えていますか?」

お題:貴社では、どういう人を「リーダー」あるいは「リーダーシップがある人」と定義していますか。
第5話 何が人を成長させるのか(堀之内氏&岩元研究員)
— 堀之内氏
リーダーは「育てるもの」ではなく「育つもの」だと考えた時に、それぞれが己の成長をどう捉えるか、ということが重要になってくると思います。
人間の成長を考える時に、参考となる一つとして「ものがたり」が上げられると思います。人類は太古の昔から「ものがたり」を愛してきました。その大きな特徴は、人間の感情に訴える力を持つため、心に入りやすい、ということです。この特徴を生かして、道徳や人生哲学、さらには政治的なプロパガンダや商品の宣伝まで、様々なメッセージが「ものがたり」の形をとって紡がれています。
実は、「ものがたり」の多くで、主人公は以下のような「成長(変化)」をたどります。
- 平和な日常
- トラブルや事件に巻き込まれる
- 新しい冒険に出る
- 大きな挫折・喪失
- 復活からの大逆転
- 大きな成長(ハッピーエンド)
「ものがたり」を考える際に大事なのは、どん底で何が起きるか、ということです。ここで絶対に守らなければいけないルールは、打開策や明るい未来は本人の努力の末に獲得しなければならない、ということです。これが偶然だったり、関係ない他の誰かが助けてくれたり、で進んだとしたら、たとえハッピーエンドを迎えたとしても、誰も納得しません。主人公が決意し、耐え忍び、立ち向かう姿に、観客は共感するのです。そういう「自分でなんとかする」環境・機会を提供することが、「育成」において重要な気がしています。
— 岩元
ハリウッド映画のストーリーラインを人材育成に生かすことができるのではないか、という視点は非常に面白いです。例えば、ある程度、業務経験を積んだ段階で困難な状況、いわゆる修羅場経験の機会を与え、それを乗り越えるための支援をおこなう。ここでは「希望」を見せることに当たります。また、修羅場を乗り越える伏線として、必要な情報やサポートを提供するなども考えられます。
※グループ内でミニダイアログ
お題:何が人を成長させるのでしょうか。これからのリーダーを育成するために、どのような機会を提供する必要があるでしょうか。

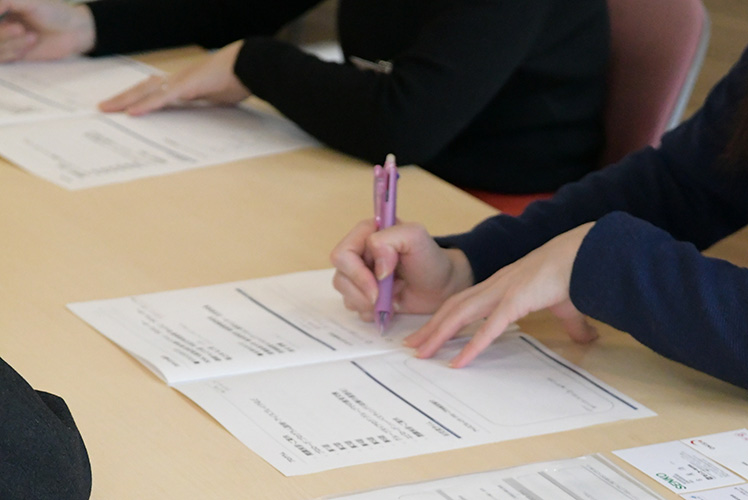

第6話 これからのリーダー育成のキーワード(全体共有)
・人を育てることは「点」ではなく、その人の「人生」に関わることなのだと感じました。熱意があるかどうか、部下を信じて任せられるかが大事だと思います。
・人生の主役は自分であるというメッセージに感銘を受けました。いわば会社は舞台です。活躍する場を与える役目があるのだと思います。
・堀之内氏の熱さ、誠実さ、真摯さに接し、これらの要素がとても重要だと感じました。ロールモデルとして今後のご活躍を期待しています。
・今回のセミナーを通して、異なる企業・組織文化を持つ方々との話し合いが重要であることを体感できました。
— 堀之内氏
僕は、プロデューサーは「希望を配る人」だと思っています。そしてそれは、限られた人、特定の人の話ではなく、誰もがそういう存在になれると思います。ハリウッドに留学した際、その道で成功しているプロデューサーや監督に話を聞く機会があると、「作品を作るために一番重要なことは何か?」と必ず質問していました。すると皆が異口同音に「それは“パッション”」と答えていました。科学的な手法や方法論が数多くあるアメリカで、当初、この回答には驚きましたが、「パッション」「熱」がやはり人を動かし、感動させるというのは、万国共通なんだな、と思い、それが僕の行動指針になりました。
「まんぷく」の企画を通し、百福さんとその成功を支えた妻の仁子さんの人生を深く知ることができました。そこから得た熱を胸に、僕は今も前を向いて仕事をしています。ここに集った皆様方とこの言葉を共有して、今回の話を終わりにしたいと思います。

