事例・コラム
プロフィール
-

内田 泰之
学校法人産業能率大学 総合研究所小学生のころから両親に連れられて歌舞伎を見始め、学生時代は都内で上演されたすべての歌舞伎公演を鑑賞。
本学では、マネジメントやビジネススキル、資格関連のセミナーや通信研修の開発に従事し、
通信研修「~世界に誇る日本の文化・伝統を学ぶ~歌舞伎入門」の開発も担当。
映画「国宝」の大ヒットなどで沸騰する「歌舞伎熱」
映画「国宝」が、大ヒットとなっています。
これは上方歌舞伎の世界を舞台にした映画で、主演の吉沢亮さんと横浜流星さんが、撮影のために約1年半にわたって歌舞伎の稽古を積んだことや、現役の歌舞伎俳優から称賛の声が相次いでいることなどが、話題となっています。
この映画をご覧になって、改めて歌舞伎に興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。
事実、この映画が公開されて以降、歌舞伎を上演している劇場のチケットが取りにくくなっているそうです。
折から、歌舞伎界の大名跡(だいみょうせき・おおみょうせき)である八代目尾上菊五郎・六代目尾上菊之助の襲名披露が、5月の歌舞伎座を皮切りに、各地の劇場で華々しく行なわれており、大盛況が続いています。
さらに、9月京都・南座でのルパン三世の歌舞伎版「流白浪燦星(るぱんさんせい)」や11月歌舞伎座での三谷幸喜氏の新作歌舞伎など、新しい作品も続々登場し、大きな話題となっています。
まさに、歌舞伎の注目度が、今、急上昇しているのです。

歌舞伎は、「イノベーションの教科書」
歌舞伎は、江戸時代から庶民に支持され、エンターテインメントとして現代まで発展を遂げ続けてきた演劇です。そのため、スターの人気を盛り上げていくしくみや、クライマックスに向けて畳みかけていく脚本や演出、斬新で華麗な衣装、印象的な音楽、美しい舞台美術など、「高いお金を払ってでも見たい!」と思わせるための工夫や、計算しつくされた興行システムが整備されています。
実際、現在行われているエンターテインメントのしくみは、歌舞伎が元になっているものが多くあります。
例えば、二枚目や三枚目といった役柄は、昔の劇場に掲げられた役者名の看板の位置に由来しますし、廻り舞台や迫り(せり)、花道などの舞台機構や、早替り、宙乗りなどの演出も歌舞伎が起源と言われています。スター中心のシステムやロングランシステム、人気スターとの商品タイアップ、一年契約制なども江戸時代から行われていました。
まさに、 「歌舞伎はエンターテインメントビジネスの教科書」 と言っても過言ではありません。
歌舞伎は、伝統的な本質を保ちながらも、現代の嗜好も柔軟に取り込み、進化し続けています。
このような創造的な姿勢は、エンターテインメント関連企業に限らず、すべての業種におけるイノベーションに大いに役立つでしょう。
もともと歌舞伎は、常識にとらわれない奇抜な格好で市中を闊歩する「かぶき者」の精神がルーツとなっています。
歌舞伎を深く知れば知るほど、固定観念を打破する柔軟な精神に驚かされ、その斬新で豊かな創造性に圧倒されるようになります。
実際、歌舞伎の発想は、作品内容はもちろん、ビジュアルにしても、演技にしても、現代人の目から見てとても斬新でエキサイティングです。
イノベーションが求められる次世代リーダーに必須の、柔軟でクリエイティブな思考の育成に、歌舞伎は大いに参考となることでしょう。
デフォルメされた歌舞伎の世界で、人間の本質的な姿が炙り出される
AIが普及し、何でも机上の仮想空間の中で完結するデジタルの世界に、どことなく不安を感じている方は、多いのではないでしょうか。
企業はお客様と経済合理性だけでは終わらない、人間的な信頼関係でつながっています。
つまるところ、実際のビジネスは、濃厚な人間関係に左右されることも少なくありません。そこには論理だけではなく、感覚や感情が絡んできます。
歌舞伎で表現されるのは、現代では希薄になりつつある人間臭いどろどろした世界です。
歌舞伎では、「親子の愛情と別れ」だったり、「生死をかけた恋愛」だったり、「現世を超越した夫婦の愛情」あるいは「命をかけた信頼関係」といった、いつの時代でも共通する普遍的なテーマを極端な形にデフォルメしたものが、純度の高い形で提示されることが多くあります。
例えば、10月の東京・歌舞伎座「義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)」の第三部で上演されている「川連法眼館(かわつらほうげんやかた)」は、皮を鼓に張られた親狐を慕って、義経の家来の佐藤忠信に化けて鼓に寄り添う子狐の物語です。狐が主人公という非現実的な展開で、早替りや狐ことばなど、歌舞伎ならではの見せ場がありますが、親を慕う子どもの情という普遍的なテーマが描かれています。
このような現実にはありえない設定でも、歌舞伎なら違和感なく受け止められるのが不思議なところです。その中で、普遍的な心情がかえって鮮明に浮かび上がってくるような構造になっているのです。
観客は、現実ではなかなか体験できないような濃厚な感情を歌舞伎の劇中で体験することで、ひるがえって現実のわが身を振り返り、新たな気づきを得ることができます。
現在は、ロジカルシンキングとITを中心としたスキルに学習が偏重する傾向にありますが、これから次世代リーダーに重視されるのは、確かな人間理解に基づくヒューマンスキルです。
歌舞伎を観ることで、忘れかけていた人間の本質的な姿に気付き、自らの生き方を再考し、ヒューマンスキルを磨くことにつながるのです。


グローバルレベルの文化理解には欠かせない日本文化の知識
歌舞伎は、2005年にユネスコの無形文化遺産に登録され、日本の伝統的な演劇として世界的に高く評価されています。
海外公演も多く行われており、日本独自の総合芸術として、海外では広く認識されています。
そのため、海外とのビジネスのお客様、特にアートに詳しい方は、歌舞伎について関心をお持ちになり、日本人なら詳しいだろうと、いろいろと質問される場合も少なくありません。
しかし、そのような質問に的確に答えられる日本人が、どれほどいらっしゃるでしょうか?
海外では自国の文化について説明できることが知的なビジネスパーソンの条件となっています。
日本文化を知らずに恥をかくのは、日本人ばかりです。
歌舞伎を通じて日本文化の深層に触れることは、異文化の理解や多様性への感受性を高めることにもつながります。
これは、グローバル企業の次世代リーダーにとっては重要な要素となります。
いま求められているダイバーシティ&インクルージョンの考え方の基本が、ここにあるのです。
歌舞伎による次世代リーダーの育成
いままで見てきたように、歌舞伎を理解することは、 「クリエイティブな思考の養成」や、 「人間理解・自己理解の促進」、 「日本文化の本質の理解」など、次世代リーダーにとって必要不可欠な要素を学ぶことに他なりません。
海外で日本の伝統文化に関心が高まっている現在、歌舞伎に関心を持つ海外のビジネスパートナーも少なくないため、観劇体験とレクチャーをセットにして歌舞伎を体験的に理解させる研修を担当部門や次世代リーダーに受講させる企業も出てきています。
本学の通信研修「歌舞伎入門」も、鉄道、建設、情報、保険、製造、旅行、教育、行政体など多岐にわたる業種で、のべ64社様にご導入いただいており、歌舞伎が研修のテーマになりうることを実証しています。
それにも増して、日常生活から一歩離れ、非現実的な歌舞伎の世界にゆっくり浸ることで、リフレッシュし活力を得て、心の豊かさを取り戻すことができます。
結局、これが、歌舞伎が何百年間提供し続けてきた一番の効用かもしれません。
意外に敷居が低い歌舞伎観劇
ところで、歌舞伎はハードルが高そうでいて、実は意外と手軽に楽しめる演劇であることをご存知でしょうか?
NHKのEテレでは、定期的に歌舞伎の劇場中継が放送されていますし、動画配信サービスなどでも映像を観ることができます。シネマ歌舞伎という、歌舞伎の舞台公演を高性能カメラで撮影しスクリーンで上映する映像作品も、各都市の松竹系の映画館で上映されています。
しかし、歌舞伎はやはり生の舞台で観るのが一番。迫力や臨場感は、やはり生の舞台を観ないと十分伝わって来ません。
「劇場で生の舞台を観ると、観劇料が高いのでは?」と思われる方も多いでしょう。
例えば、東京の歌舞伎座では、毎月歌舞伎の公演があり、特等席や桟敷(さじき)席のチケットは20,000円程度しますが、3階B席なら5,000円程度です。(昼の部、夜の部の二部制の場合)
同劇場には「一幕見(ひとまくみ)席」といって、1幕(多くの場合1演目)1,000~4,500円程度で見られる席もあります。(2025年11月時点)
大阪や京都、名古屋、福岡の劇場では、年何回も歌舞伎が上演されていますし、毎年各地を周る巡業も催されています。

百聞は一見にしかず。
まず、歌舞伎を劇場で生の舞台で見ることから始めてみましょう。
初めは戸惑うことがあるかもしれませんが、次第に慣れてくると理解が進み、上記で述べたような効用が実感できるようになります。
簡単に導入できる通信研修「歌舞伎入門」
しかし、一概に歌舞伎といっても、演目の幅は非常に広く、人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)をベースに作られた重厚な義太夫狂言(ぎだゆうきょうげん。この場合の「狂言」とは、演目のこと)から、美しい舞踊、庶民の生活を描いたわかりやすい世話物(せわもの)、現代的な新作歌舞伎まで様々です。
セリフも現代語に近くてテレビの時代劇と同じ感覚で楽しめるものがある一方で、中には、あらかじめある程度の知識がないと理解しにくいものがあるのも事実です。
よって、歌舞伎を観に行くときは、その演目についての知識を少しでも持っていると、当日、戸惑うことは少ないと思います。
また、昔は一日かけて一つの長いお芝居を始めから最後まで通しで上演するスタイル(通し狂言)が主流でしたが、現在ではその中から名場面だけを抜き出して上演し、それを何演目か組み合わせる興行が多くなっています。(先ほどの「義経千本桜」は、通し狂言ですが三部に分けて全体を上演する三部制となっています。)
そのため、上演される幕の前後の筋をあらかじめ知っていれば、登場人物の言動の意味がよりわかりやすくなります。
つまり、歌舞伎を見るときにある程度前提となる知識や、代表的な演目のあらすじや鑑賞のポイントなどを知っておくと、単に「きれい」「面白い」といった表面的なこと以上に、歌舞伎の奥深い世界を寄り早く楽しむことができるようになるのです。
このような歌舞伎の基礎知識と代表的な演目の鑑賞のポイントをコンパクトに短期間で学習できるのが、通信研修「歌舞伎入門」です。
歌舞伎の製作は、現在、松竹株式会社が主に手がけており、「歌舞伎」ということば自体も同社の登録商標です。
この「歌舞伎入門」は同社のご協力をいただいて開発されており、教材も同社の監修ですので、舞台写真も多く、リアルで楽しい内容となっています。
次世代リーダーに必要な要件のいくつかは、歌舞伎によって養成できることは、上で見てきたとおりです。
次世代リーダー育成だけに限らず、日本文化の的確な理解に、確固としたヒューマンスキルの醸成に、またアートに触れることでクリエイティブな思考の育成に、ぜひ通信研修「歌舞伎入門」で、"歌舞伎思考"を取り入れてみてはいかがでしょうか?
「歌舞伎入門」の詳細はこちら!
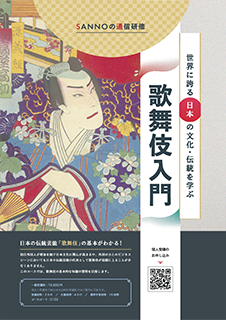
~世界に誇る日本の文化・伝統を学ぶ~ 歌舞伎入門
「歌舞伎」について、基本的な知識や約束事、主要な演目のあらすじや見どころなどを、総合的に理解する講座です。人気演目の『白浪五人男』をDVDで鑑賞しながら、「鑑賞の手引き」で具体的に見どころや名セリフへの理解を深め、歌舞伎の豊かさや奥深さを堪能します。
- 参考:歌舞伎美人(https://www.kabuki-bito.jp/)
